報道取材を受けて(朝日新聞,NHK,よみうりテレビ)
東大阪市の助成を受け、おこなっている研究に関して、1998年の暮れから1999年明けにかけて、新聞ならびにテレビの取材に応じた。朝日新聞、NHKの「おはよう関西」「発信基地」、よみうりテレビの「ズームイン朝」である。はっきりとした研究テーマに関しての取材は初めての経験だったが、つくづく研究というものが、報道と馴染まないものであることを実感し、今後は遠慮しようと思った。
その一番の理由は、マスコミは、あらかじめ特定のイメージを持って取材をしており、そのイメージと食い違うことについては報道したがらない(実際に報道しなかった)ということである。また、本当に分かっている以上に、はっきりとした結論を求めたがることについてもうんざりした。すなわち、学問的真実(ことばの真の姿といってよいだろう)にはあまり興味を持っておらず、いくらこちらが丁寧に説明しても、結局は彼らの最初のイメージ通りの番組になってしまうからである。この点は、テレビ報道において特に感じた。
次から次へと、視聴者が求める目新しい番組を作っては、流し続けていかなければならないというマスコミの本質と、一つのことを何年もかけてじっくりと調べ、真実を追求していくという、一般人にとって面白いとは思えない研究の本質とは、相容れないということだろう。
われわれの仕事は、学問的真実を追求することであって、それを一般の人に、簡単に一言で伝えることではない。取材中、「こちらからお願いして取材してもらっているわけでもないし、番組にならないようならおやめになったらどうですか。」と何度言ったことか。こう言うと、象牙の塔にこもっているように聞こえるかもしれない。大学の教師である以上、教育というものを避けて通ることはできないが、教える相手はあくまでも学生なのであって、予備知識のまったくない一般人ではないと考える。このことを改めて認識させてくれたことが、今回の取材の数少ない成果ということだろうか。
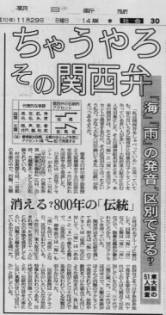 朝日新聞
朝日新聞
朝日新聞大阪本社版1998年11月29日(日)社会面の記事。取材した記者は、勉強熱心で好感が持てた。記事の内容についても事前にファックスで確認があり、この手の取材としてはきちんとしていると思った。しかし、実際に新聞記事になってみるとがっかりした。この「ちゃうやろその関西弁」というタイトルは、校正段階ではどこにもなかったからである。ご丁寧に、一面の内容紹介欄に、当時来日中の江沢民主席の名前の倍近いポイントで大書してある。この記事内容が中国の国家主席の訪日より重要とは、研究している者にとっては光栄な話であるが、そんなわけはない。どの段階でこの見出しになったのか?
いずれにせよ、この見出しによって、この記事の学問的価値は損なわれてしまったと言える。それは、この見出しが学問にとって重要な、客観性とはかけ離れており、主観的、感情的に、このアクセント変化を悪いものと断じ去っているからである。おそらく、この記事を読む一般読者は(場合によっては専門家さえ)、記事の内容は覚えずに、見出しの印象のみを記憶することだろう。記事を読んで、少しでも理解してくれれば、まだましかも知れない。記事そのものをろくに読まず、この見出しとわれわれの名前を結びつけるだけの人が多いだろう。当人達は一言もそんなことは言っていないのにである。
はたして、ここに述べたようなことを、記事を作る側では認識しているのだろうか。分かってやっているなら悪質だが、おそらく意識しないままに、こういった見出しをつけているのではないか。要するに、取材はしたが最後には自分(ないしは社)の日頃潜在的に考えている思想が表に出てしまったということだろう。
ズームイン朝(よみうりテレビ) 画面
1998年12月16日(水)、よみうりテレビ『ズームイン朝』の7:47〜7:54に放送された。あまり見たことのない番組だが、取材を受けるべきではなかったと思う。研究室において、私以外の者に常識のない態度をとる、取材時に約束したことを守らない、フリップのアクセント表記の記号を勝手に作る(下の図に示した通り)、そして、われわれが調査した結果得られた数字を、自分たちの街角インタビューの結果明らかになったかのように流す、インタビュー時の田原の返事に対する元の質問を、都合のよいものに取り替えるなど、あまりにも問題の多い取材、番組だった。
番組分析
局 名:読売テレビ 1998年12月16日(水) 7:47〜7:54番組名:『ズームイン朝』コーナー名:おもしろ発見タイトル1:「関西弁が無くなる!?」(コマーシャル前の予告時)タイトル2:「関西弁の伝統が消える!?」(番組冒頭時)
1.コーナー紹介(4秒)
関西弁がピンチ
2.街角インタビュー(27秒)
通天閣付近で街頭インタビュー
関西人にとっての関西弁とは?
命、人情味、魂、関西人のすべて。切っても切り離せないものである
この関西弁が崩壊の危機に
3.アナウンサーのあいさつ(21秒)
関西弁を喋る若者の間で、ある重大な変化が起こりつつある
4.大阪樟蔭女子大学と日本語研究センターの映像による紹介(13秒)
5.田原がアナウンサーにアクセントのテストをおこない、結果について解説する(54秒)
「海、空、雨、声」の発音
この4つが区別無し→伝統的なアクセントが失われている元々の大阪のアクセント−最後が少し下がるアクセント
6.アナウンサーが伝統的な大阪アクセントで発音(18秒)
7.平安時代の漢和辞典「類聚名義抄」を元に類別表の提示(59秒)
日本語は、語尾が上がったり下がったりするアクセント
関西弁は、京都や奈良など昔の都が含まれる地域であり、
古いアクセントが色濃く残る貴重な言葉である
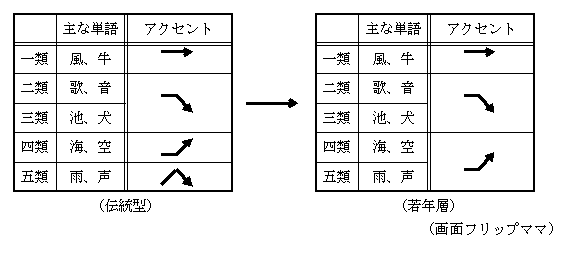
8.実際に街で調査(45秒)
大阪駅にて街頭インタビュー
田原と村中のおこなった結果の結果
−50人中昔ながらのアクセントを使っているのは、40代以上90%、30代30%、20代以下ほぼ0%
9.田原の解説(51秒)
アクセントの区別が失われる理由など
昔のように大家族で一つの家に住んでいれば、方言は伝承されやすい
現在のように核家族が中心の社会では、世代間の会話が減ってくることが背景にある
また、縦の関係より友達など横の関係を重視する社会的な風潮があることも原因であるいったん区別がなくなってしまうと、二度と元に戻すことはできない
アナウンサーのコメント
関西弁のアクセントがどんどん無くなっていく→日本の方言の中にはそういう地域もある
10.未来の関西弁−八百屋の店員−(57秒)
八百屋の店員が「ミテッテヤ」「コウテッテヤ」「ヤスナッテル」などを間違ったアクセントで発音してみせる
近所の主婦と柿(カキ)のアクセントについて掛け合い調で話す
11.アナウンサーのまとめ(43秒)
アクセントの変化の原因として、テレビなどの影響が考えられる
全国のアクセントも変わってきている(例えば、東北弁、名古屋弁)
伝統型アクセントの確認
東京本局の福澤アナウンサーの意見
関西弁はとりわけ生命力が強いと思っていた
伝える能力が弱まってきているのでは?
危機感を覚えた
おはよう関西(NHK大阪) 画面
1998年12月14日(水)、NHK『おはよう関西』の7:36〜7:41に放送された。NHKの取材の態度は、総じてよかったと思う。取材にある程度時間をかけていたし、番組の作り方も丁寧であった。5分で説明、理解できる内容に限るという報道姿勢が貫かれていた。具体的には、類別語彙、『類聚名義抄』といった専門的な術語、書名は避ける、とりあげる単語を「声」の一語に絞る、さらに単語言い切りの形のみを扱うなどである。また、視覚的な効果(CG)が、内容を誇張しない程度に適切に使われており、報道番組制作におけるNHKの技術的な底力を感じた。このページの最初に述べたような本質的な点については、問題が残るが、担当したディレクターは、できる限りのことをして、内容を視聴者に伝えようという努力をしたと評価できる。
番組分析
局 名:NHK 1998年12月14日(月) 7:36〜7:41番組名:『おはよう関西』コーナー名:リポートタイトル:「変わる関西弁」
1.アナウンサーが「声(コエ)」のアクセントを発音(38秒)
アナウンサーがテロップを元に説明する。
家族の中でも発音が違っているかもしれないことを示唆
関西弁が変わりつつある
2.街頭でコエのアクセントを発音
石切で老年に(38秒) アメリカ村で若者に(28秒) 石切の60代以上の4人がほとんど低いところから一度上がり、また下がるアクセント アメ村の10〜20代4人はほとんど低いところから上がったままのアクセント世代間の違いに気づいている若者の話
3.大阪樟蔭女子大学日本語研究センター(1分26秒)
パソコンの画面でアクセント調査時の録音を流す
田原は10年ほど前から大阪の方言の研究をしている 1999年春に東大阪市調査で51人に調査をおこなったこの結果、世代によってアクセントが変化していることがわかった
パソコン画面で15人の発音を流す 60〜40代は伝統的なアクセント、30代では新しい型が混ざり、20代はすべて新しい型になる 伝統的なアクセントが30代から崩れているアクセントは無意識に発音しているので、変化が無意識に進み、知らない間に変わってしまう
いったん変わってしまうと、もう元に戻せない
4.現在の関西弁の2音節名詞のアクセントについて(35秒)
現在、40代以降は、下の図のように4種類のアクセント型があるが、 30代以下は、3種類のアクセント型になりつつある
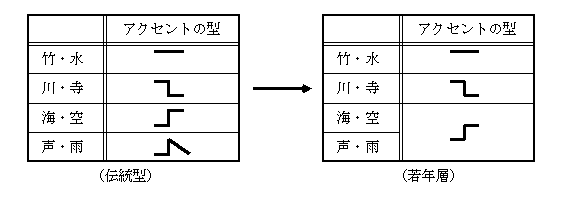
5.平安時代末期に書かれた漢和辞典について(57秒)
「コエ」という字の横にアクセントの点が付けてあり、当時のアクセントがわかる
900年ほど前から「低いところから一度上がり、また下がる」という特徴を持っていた
6.田原の解説(25秒)
年輩の人の若者に接するにあたっての意識に問題がある
年をとった人が「こんな方言を言ってもわかってもらえないんじゃないか」と思っている
この遠慮は、ことばの面においてもことば以外の面においても見られる
ことばや文化を伝えていくという点でこういった態度は影響を与えているだろう
7.まとめ(29秒)
若い女性4人へのインタビュー(雑談的意見)群衆をバックにナレーション
発信基地(NHK大阪)
もう一件、1999年2月14日(日)、NHK『発信基地』で30分番組として放送されたものがあるが、1999年6月19日現在、2回生の演習の中で、番組分析をおこなっている最中である。概要は、前半は4類について大阪大学の真田信治教授が、後半は5類について田原が解説するという形式をとっている。その間に、「やんちゃくれ」の方言指導の状況、アナウンサーと河内厚朗の話、桂米朝ら落語家の意見が織りまぜてある。