welcome to CDA-Room
臨床歯科麻酔メーリングリストのお知らせ
(CDA=Clinical Dental Anesthesia−ML)
臨床歯科麻酔メーリングリストのご案内
【CDA-MLプロフィール】
歯科医学のなかでマイナーな領域であった歯科麻酔学でしたが、日本中のほとんど
の歯学部にも講座が設けられるようになり、認定医を始めとした多くの研修を受けた
歯科医師を輩出しています。
しかし、せっかく研修を受けながら、その活躍の場は、
未だに大学以外にはほとんど見いだせないのが現状です。
大学病院での主な歯科麻酔
医の業務は、口腔外科の全身麻酔であり、これは歯科医師が医学的な全身把握を習得
するためには確かに有効です。
しかし、研修した歯科医師が、一般的な歯科臨床でも
その知識と経験を展開し活躍することが望まれています。
研修後の活躍の場がほとんどないことから、大学外で歯科麻酔の意義、重要性をア
ピールすることは、これまでほとんど出来ませんでした。
しかし、現在、日本の医療は変わりつつあります。
高齢者を始めとする福祉を、視野の中央に入れるべき時代に
なってきました。
こうした高齢者の在宅医療や、内部障害を含んだ障害者の治療にお
いて、歯科麻酔の研修は歯科医師の卒後教育に不可欠な領域になってきています。時
代がようやく歯科麻酔に追いついてきたのです。
こうした臨床中心の歯科麻酔の領域を臨床歯科麻酔として、広く認識させるべきで
はないでしょうか。歯科麻酔学会総会では、大学講座が主体となり運営されていまし
たが、平成8年に、開業歯科麻酔認定医フォーラムがタイムリーに開催されました。
今後、歯科臨床で活躍している先生方の意見交換や経験の発表の場
をどんどん作らなければなりません。
この臨床歯科麻酔メーリングリストがその端緒になればと思い、ここに立ち上げる
こととなりました。
●メーリングリスト(ML)とは?●
メーリングリストとは、メンバーが登録したグループに電子メールアドレスを与え、
そこに電子メールを送ると、自動的に全てのメンバーにそのメールが配送されるシス
テムです。
ある議題についてメンバー全員で議論をしたり、情報交換するには非常に
有用です。自分の都合の良い時間帯にメールを読み書きすることで、日本中の参加者
と議論や情報交換ができます。
【参加資格】
歯科麻酔の研修経験のある歯科医師
ただし、運営委員によりこの他に参加を認めることがあります。
参加を希望する方は、以下のアドレスにメールをお送り下さい。
cda@mb.infoweb.or.jp

歯科麻酔学会(97年度)発表原稿
インターネットの歯科麻酔における臨床利用について
静岡県開業1)・千葉県開業2)・埼玉県そうか光生園3)
◯望月 亮1)・古屋 浩2)・加藤仁資3)
昨今、インターネットに代表されるコンピュータ通信が、広く一般に
浸透しつつあります。この機会を捕らえて、今回私たちは、
歯科麻酔を議論のテーマとしたメーリングリスト(以下MLと略します)と、
ホームページによる情報提供を試みましたので、
その成果をご報告いたします。
今回私たちが選択したMLとは、
「登録者の電子メールを登録者全員に自動的に送付することにより、
グループ内の情報交換を行うサーバーシステム」
のことです。
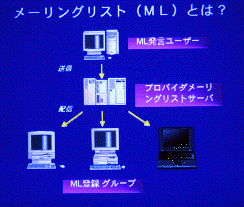
スライドに示すような仕組みで、任意の話題について、
参加者は自由な議論に参加することが出来ます。
本年1月より、このようなMLの一つとして、
「臨床歯科麻酔メーリングリスト」(略称cda)の運営を始めました。
運営委員の3人がいずれも大学に所属していなかったため、
大学のサーバーは使用せず、プロバイダのサービスを用いました。
これは、大学のサーバと比べて自由度はありませんが、
メンテナンスに労力を要しないという利点があります。
プロバイダは富士通系のinfowebを選択し、現在までほぼトラブルなく
稼働しております。
cdaは1月から試験運用、4月から準公開としました。
参加資格は原則として
「歯科麻酔の研修経験のある歯科医師」
としました。
歯科麻酔についての真剣で内容のある討議を期待したからです。
ただ、将来には広く一般に公開して、歯科麻酔そのものの社会的認知に
寄与出来れば、と考えております。

9月5日現在で、参加者の総数は47人、平均年齢は37.4才でした。
これはすでにいくつかあるさまざまなコンピュータネットワークの中でも、
かなり高い方に位置しています。
参加者のメールアドレス、勤務先の分布はスライドに示すとおりです。
開業医と非大学勤務医で、全体の6割以上を占めています。
また、参加者のうち、歯科麻酔学会員は全体の84%、
歯科麻酔学会認定医は30人以上を数えました。
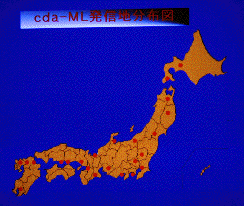
参加者の出身大学は23校,住所は北海道から鹿児島県まで日本各地に及んでいます。
また、大学院学生や開業したての先生から、大学の歯科麻酔科教授に至るまで、
幅広い層から参加をいただいています。
このように広範な層からの参加が得られたのは、やはり一般プロバイダのサービスで
運営しているメリットだと思われます。
次に、実際の議論の内容を紹介いたします。
スライドに示すとおり、従来の制約にとらわれない、
さまざまな内容の議論が展開されています。
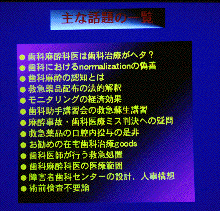
これは、第一線の臨床医が参加者の多くを占めていた、という背景を反映しています。
症例報告、麻酔法へのアドバイスなどがみられるのはもちろんですが、
歯科麻酔科医の歯科治療技術、
ライセンスと歯科麻酔の問題、
など、スライドに示すごとく、歯科麻酔、歯科全身管理に関して
このMLならではの突っ込んだ話題が目を引きます。
次に実際の議論の一例をお目にかけます(スライド省略)。
この一連のスレッドでは、歯科麻酔の社会的認知が話題になっています。
開業にあたって歯科麻酔をどのように位置づけていくか、という疑問から端を発し、
歯科麻酔が普遍的な社会的認知を獲得するために、現在横たわっている問題は何か、
それらをどのように解決して行かねばならないのか.....
これらについて、熱のこもった議論が展開されました。
MLが活気があるかどうか、を測る一つの目安として、多くの発言を、
まんべんなく多数の参加者から得られているかどうか、が指摘されます。
現在多くの医療系MLでは、管理者は発言のactivity確保に苦心惨憺して
いるのが実情です。
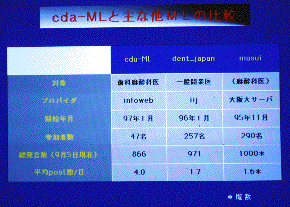
cdaの9月5日までの総発言数は866を数え、
一日平均あたりのpost数は約4.0でした。
ここにコントロールとして採り上げましたのは、
開業歯科医師を対象とした代表的な歯科ML「dent_japan」です。
参加者257名、一日の平均post数1.6前後となっています。
また,masuiというのは,[麻酔ディスカッションリスト]一般の麻酔科医の
MLです.このMLのアクティビティもほぼ同様です.
もちろん、発言が多ければいいというものではありません。しかし、
cdaはdent_japanやmasuiのわずか4分の1にも満たない参加者数で、
それ以上のactivityを維持しています。
これは、参加者一人一人の歯科麻酔へのテンションの高さを物語るもので、
誇ってよい数字と思います。
これらの議論のうち、社会的意義にあるものについては、症例報告などでは、
対象者が特定されないように 十分配慮の上、ホームページを開設して
公開しております(スライド省略)。
このホームページには、過去の議論のテーマが収録されており、
新たな参加者が、運営委員に電子メールでこれらのログを請求できるように
なっています。
また、MLの概略をインフォメーションし、
参加申し込みが可能な設定もなされています。
実際に、このホームページを見て参加した先生も少なくありません。
スライド 考察 cdaの意義
1 参加者の地域、環境、地位にとらわれない自由で活発かつ真剣な議論。
2 学会などで採り上げられにくいテーマについての突っ込んだ意見交換。
インターネットの大きな特色の一つに、参加者の社会的階級、身分などにとらわれず、
平等な発言、議論が約束される、という、いわゆる「水平化」が挙げられます。
このcdaでも、構成する参加者は、年齢,出身医局,居住地,歯科麻酔への接し方など
実にさまざまな環境にあります。しかし、こうした背景にとらわれることなく、
「歯科麻酔、歯科における全身管理」という大きなテーマの下に、
自由な発言、討論が実現しようとしています。
このような議論環境は、従来の直接的コミュニケーションからは、
なかなか生まれにくいものであり、インターネットを活用した
何よりも大きな意義であったと考えています。
結語はスライドに示します。
スライド 結語
1 「臨床歯科麻酔メーリングリスト」を1月から運用し、
現在までに50名近くの参加者、800以上の発言を得た。
2 インターネットの特徴を生かした、従来の制約にとらわれない
有意義な議論の場として、今後の発展が期待される。
歯科麻酔に関する、フレキシブルで有意義な議論の場として、
今後もこのcdaを大切に育てていきたいと願っております。
